昨夜は家の中にいても雨音が聞こえて雷も鳴ったりで、少し怖いくらいだった。
それでもそんな音を聞きながらすんなり眠りに落ちていたようだ。
打って変わって晴天で迎えた今朝は、強風が吹き外干しした洗濯物が早く乾きそうだ。
夜に気づいたが、やっぱり森を歩いたから虫に刺されるはずで、首の後ろが数カ所腫れていた。
でも凄く痒いでもなく、この程度で済んだのも折りたたみ傘を振り回していたおかげだったかもしれない。
今日は息子が休みなので送迎はないが、ミスドのラインギフトを貰ったので買いに行く。
かなりの肥満の息子だから本当は有り難くないけれど、楽しみが少ないから仕方ないかなと思う。
そして今日は米がもうあと僅かになったから、買わないとならない。
備蓄米というのはもう出ているのか知らないが、手に入れるとしたらちゃんと販売日を確かめて並ぶのだろう。
米を蓄えておくほど余裕はないから、無くなりそうになって買いにきたけれどいまいち世の中の動きがわかっていない。
結局”キタノイロドリ”という3180円(税別)の米を買って来た。
宮尾登美子さん「櫂」
最初は言葉使いに慣れずに読み切れるかどうか不安だった「櫂」」だが、後半になって一気に読むペースが早くなった。
昔身売りが盛ん?だった頃に紹介業をしていた夫が、よそに産ませた子を引き取って育てながら好きではない家業を支えて後に身勝手な夫に離縁される女性が主人公だ。
時代がかなり違うからこの夫婦の関係が現代でならもうパワハラでしかないのだが、昔はこうだったんだと思うしかない。
女性の地位が低すぎて夫に逆らうものなら、鉄拳制裁もやむなくまず間違っていても謝ることなどない。
けれど夫の心の内なども書かれているから、単純に「こいつめ!」と怒りが沸き上がる訳じゃなく男尊女卑が当たり前の時代だったということだ。
夫がよそに産ませた子を引き取って育てることを最初は拒否した主人公に、妻が口答えすることに怒って気絶するまで殴るシーンとかがある。
その際に仲立ちした夫と同業者の女将が、折檻する様子をただ当たり前に眺めている様子がありこういう折檻が芸妓娼妓業ではなされているのが伺える。
その世界では折檻も教育の一環として通用していたようだし、身売りの身でありながら逃げたとなったら連れ戻されて酷い目に遭うらしかった。
今も人身売買はどこかであるのかもしれないが、その当時は食べるものもなくて娘を売るということはよくあったらしい。
でもそんな中で一流の芸妓さんになったり、年季を務め上げて借金をちゃんと返済する人がいれば逆に借金まみれになり身を落とすこともあっただろう。
「二人キリ」の阿部定さんなどはあちこちと渡り歩いたようだから、なかなか借金返済が終わらなかったのかもしれない。
「櫂」の中で夫の岩伍が家に連れてくる娘を「此の子等は家に居るより此処に居る方が幸せ」というくらいで、親の博打好きや放蕩者で切羽詰まった金に娘は身売りされてしまう。
岩伍の妻である喜和も”昔は働いても食えぬ為の米代であったものを、今では親の不心得というのがおおかたの理由”と嘆く。
どこまでも女性は身分が低く売られるというその稼業自体が、素人の喜和にとっては馴染めないままそれでもそんな思いは心に押し込めて稼業を務める。
夫がよそに産ませた子であっても育てるうちに強い絆が生まれて、綾子という名前の女の子はやがて喜和の生きがいとなる。
実の息子も子沢山の家族を支えるのに夫と同業者となり、喜和の心の支えは綾子だけだ。
夫の岩伍は戦争の景気により、芸妓や娼妓(または慰安婦)などの手配で多忙を極めるようになる。
自宅とは別に事務所と称して住まいを借りるが、戦場に送り込む仕事が繫盛して多忙であったのと同時に別の女性とも暮らし始める。
戦争で裕福になるのは武器商人だけじゃなく、こういった商売も当然大きな利益を生んだらしい。
こういう人たちが外地に駆り出され、どんな結末を迎えたが想像以上に惨い結果になったと思う。
ある時ほとんど寄り付かないに自宅にやって来た岩伍が喜和と言い争う姿を見て、逆上した綾子が岩伍に刃向かった。
女でありながらしかも父親に刃向かった綾子、そんな育て方をした喜和を許せない岩伍。
これ以上綾子を喜和に預けることは出来ないと言い残し去った岩伍から、後に離縁状が息子の手によって突き付けられる。
当時は離縁されるというのは、相当の一大事だった様子が窺える。
岩伍の考えで、喜和と綾子は引き離されることが否が応でも決定となる。
どうあがいても流れに逆らえない喜和が悲しいし、何よりも岩伍という男性を心の奥底でいつまでも思っているのが自分には解せない。
裏切られてもいい思い出とかがあったのか、喜和が一途な女性なのか、この時代の女性が尽くして当たり前なのかもしれない。
最後まで寄り添ってくれた綾子と、泣く泣く別れる準備をする喜和を描くシーンは映画「八日目の蝉」を思い出した。
「八日目の蝉」は不倫相手の子ども(赤ん坊)を誘拐した女性が、逃亡しながら数年育てた子どもとの絆と別れが描かれていた。
”生みの親より育ての親”という言葉があるが、まさにその通りで誘拐犯で捕まってしまった女性は勿論悪い。
けれど親として信頼関係が出来ていた女性と離された子ども、本当の両親とどの人物にとっても不幸な未来が展開されていた。
「櫂」では綾子を岩伍の家まで送るハイヤーに同乗した喜和が、途中で車から降りて別れを告げる。
1人になった喜和が思うことが全く「八日目の蝉」のシーンを思わせる。
“生まれたばかりの綾子を手離す辛さより、十三年間手塩に掛けた綾子を手離す辛さがどれだけ深いか”。
身を引きちぎられる辛さを想像するが、喜和はそれでも闇夜を歩き出す。
大病をしたのち全てのものを取られ気落ちするしかなかった喜和の心を思うと、ふと涙ぐみそうになった。
題名の「櫂」は夫婦のあり方を表しているのだろうか、だとしたら夫婦の船は上手く漕ぐことが出来ず岸にたどり着けなかったことになる。
夫婦は結局は他人だから仕方ないと思う。
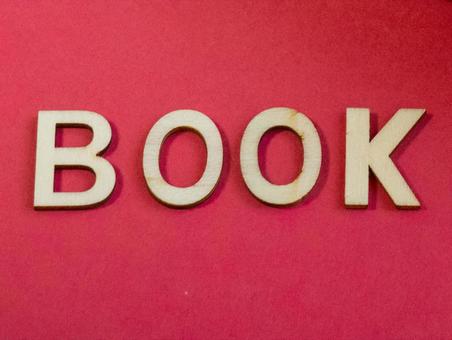


コメント