昨夜は布団に入ってから見るスマホを8時半には枕元に置いて、すぐに寝入ったようだった。
次に目覚めた時にスマホを見るとまだ日は変わっていなかった。
更新されていた坂上忍さんのブログ等を読んだりする。
そのうちに日が変わったので、ティックトックのポイ活を少しだけやって再び眠る。
次に目覚めた時間は3時26分。
今日は息子が早朝からの仕事なので、息子の起きる音で目が覚めた。
自分から目覚めない時は、若干の睡魔を引きずっての起床になる。
例えば自分が早く目覚めて起きる時間までポイ活をしながら過ごすのと、起こされたように起きるのとでは当然寝起きの状態が違う。
まだ学生の時は起こされて起きるのが多く、それが若さかもしれなかった。
今は念の為アラームをかけておくも、大体はアラームを解除して起きる。
それが年を重ねた証拠なのかもしれないが、今日は眠いと思いながら仕方なく起き上がった。
ウォーキング
今日もいつもの河川敷にやって来た。
天気は曇りで風はなく暑くも寒くもない。
スノーズボンも車には積んで来たが、履かずに歩いてみる。
ズボンの下は念の為ヒートテックにしてみたので、多分寒くは無い。
ジョギングしている人などはもう既に半袖短パン姿で、自分とはえらい違いだ。
歩いている人もいるが、最近は走る人の姿が多くなってきた。

まだ半袖は着ないけれど、夏用の服も出すべきか。
そう言いながらも冬のダウンなどはまだクリーニングに出していない。
もしかすると寒い日があったら・・・特に早朝が寒かったらと思うとまだクリーニングに出せないでいる。
歩数や時間を気にしないで歩ける早朝の日は、それだけで気分がいいし虫もまだ活動していないのが嬉しい。
今日も桜の蕾を確認するが開花は少し先だと思うし、まだ木々も色づいていない。
河川敷よりも街中や住宅地の日の当たる場所の方が開花している。
「ミカドの淑女(おんな)」
林真理子さんの著書「ミカドの淑女」をやっと読み終えた。
下田歌子という女性は「皇后は闘うことにした」で初めて知った名前。
でもその下田歌子の周囲に出てくる登場人物は、歴史をあまり知らない自分でも聞きかじった人がたくさんいた。
伊藤博文を筆頭に乃木希典・山縣有朋・幸徳秋水など、何をした人か分からなくても聞いたことがあるという名前が出て来た。
他にも沢山の名前はあったが、代表的で自分が覚えているのはこの4人だった。
平民新聞の記事があまりにも読みづらくで、意味が分かるまでには至らなかった。
学生時代に古語辞典を使った勉強があったと思うが、多分あの辞典を引きながらじゃないと意味が理解出来ないんじゃないだろうか。
国語は好きだったが古典は全く覚えていないからきっと苦手だったのだと思う。
一通り記事を読むも何となくでしか意味はわからなくて、きっと半分も理解していなかった。
それにしても伊藤博文という人物が正に”英雄色を好む”を地で行く人だったのかと今にして知った。
日本のために尽くした人なのだろうけれど、男尊女卑の時代だから仕方ないのか林真理子さんの筆致だとどうしようもない強欲じーさんぶりだった。
下田歌子という女性も秀でた才能で、当時の女性として最高の地位や栄誉をつかみ取った人物だ。
特に当時の皇后に引き立てられて、女官として高い地位を得て教育係のような役目を仰せつかっていた時期もあって寵愛の程は凄かったらしい。
主に皇族の子息だとか上流階級の子女の教育に力を注いだようだ。
教育が受けられるのは明治の時代なら一握り程度で、識字率はきっと低かったと思う。
確か自分の母の親(自分の祖母)は字が書けないとか読めなかったと聞いたことがあるから、農民ならそんな人もいたと思う。
今、夫が見ている韓国ドラマで「宮廷女官チャングム」(ドラマ自体はかなり古い)のチャングムより、下田歌子という人は位としては高そうに思う。
でも賢さと秀でたものがあるところはチャングムをイメージしてしまう。
女性としては高い地位や名誉ある職を得ていたと思われる下田歌子。
けれど平民新聞に下田歌子は”妖婦”という言われ方でスキャンダルが報じられた。
沢山の男性と関係を持つ危険な女性という噂が広まる。
本当のところは分からないが、言わば伊藤博文の女性版とでも言ったらいいのか。
下田歌子と関係を持ったと思われる男性たちが、スキャンダルの火消しに奔走するも結局下田歌子は学習院での役職を降ろされて話は終わる。
ウィキペディアで下田歌子を見ると騒動以前もその後も活躍は目覚ましい。
外国に訪問することも多かったらしく、昔の時代の女性の先駆者であったのだろう。
それほど長い話じゃなかったけれど、とにかく宮中の用語に翻弄されたというか自分が馴染めなかっただけなのだろうけれどページをめくるのに時間がかかった。
やっと最後までたどり着いたというのが感想だ。
女子教育に心血を注ぎ信望もありながらスキャンダルにもまみれたというのは、それだけ引きずりおろしたいという者がいたからだろう。
時代がそうなのか女性の活躍を許さないという反発をこの本から感じるし、出る杭は打たれるようなことは今もあると思う。
この本じゃないが何か別の林真理子さんの本でもそんなことを感じたことがあった気がする。
林真理子さんがコピーライターとして登場した時にも、色んな言われ方をしたと思うからその時の記憶だろうか。
才能を妬むのは女性よりも男性の方が強いと言うような感じだった気がする。
自分には何もないから気楽だが、「ミカドの淑女」はしっかり読み取れた気がしない。
またしても自分の理解力の乏しさがわかったくらいだ。
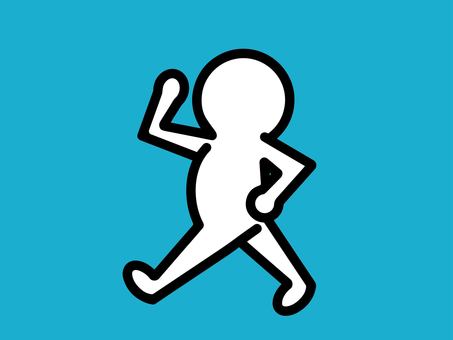

コメント