昨日幼なじみの友人から来たラインには帯状疱疹のワクチンを近々打つとあった。
友人はコロナワクチンもちゃんと数をこなしているし、今回も当然のように帯状疱疹ワクチンを打つと言う。
以前会った高校時代の友人の1人もすでにワクチン接種の1回目を終えていた。
水疱瘡には自分も子供時代に罹ったと思うから、帯状疱疹にかかるかもしれないがそれでもワクチンは副作用が怖くて未だに迷っている。
誰かが打つから自分もというようにはならなくて、もう少し考えてみようと先延ばししている。
ウォーキング
早朝から仕事の息子を送る時は空気がヒヤッとして、車の窓ガラスも白くなっていた。
今日はいつもの河川敷にやって来た。
半袖に上着を羽織って丁度いいくらいで、まだ空気は涼しいし風はほどほどにそよいでいる。
朝のうちに歩けるのはラッキーな事だ。
ここなら森と違って虫はさほど気にならないはず。
今朝の寒さ?から、不安になってまたしても腹巻とレッグウォーマーを身に着けてきた。
歩き終えたら外すつもりだけど、自分の用心は度を超えているかも。
寒い季節は当然のように太陽の方向に足が向くけれど、暑くなると自然に太陽に背を向けて歩き出していた。
自分が歩く方向に犬を3頭連れた女性が見えて来た。
自分は土手の上を歩き、女性は土手の下を歩いていた。
その女性とは2回程挨拶を交わした事があるが、とても話好きで一度止まったら会話がなかなか終わらない。
3頭の犬も大人しくていつものことなのか諦めが早く、大人しく辺りに座り込むのだ。
恐らく女性は帰りは土手の上を歩くはずなので、自分が戻る時は土手の下を歩くことにしようと思っている。
連れている犬は可愛いし女性もお喋り好きなだけでいい人のなのだろうけれど、何処で会話を切り上げたら良いのかが難しく出来たら挨拶を交わす程度がいい。
振り向くと女性は出会った人と会話しているようで、多分顔見知りの人がたくさんいるのだろう。
今日は河川敷から先にある橋を渡って見ることにした。
久々の橋は風が穏やかで天気も良くて車の往来はあるけれど、まだ早い時間なのでひっきりなしでもない。
橋の上を見上げてみる・・・たしか以前新聞の編集余禄にこの橋を見上げたら何かが見えるように書いていた人がいた。
大体どんなことが書いてあったかもとっくに忘れてしまったから、何度か見上げて見たが何も分からなかった。
橋を渡っていてこの橋の距離はどのくらいあるのか、歩きながら500mくらかなと考えたが実際はもっと短くて369mらしい。
予測するのは難しいものだ。

自分のウォーキングは1人になって頭に浮かぶことを考えたり、独り言を言ったり歌を口ずさんだりを楽しむための自分だけの世界だと思う。
「櫂」は四部作
昨夜は読み終えた「櫂」の解説を読んで見た。
本によっては最初に解説を読んでしまうことがあるけれど、最後に読むために後ろにあるのだし大抵の人が最後に読むだろう。
林真理子さんは、宮尾登美子さんの本は「櫂」から読むのがいいと言っていた。
解説の方も”「櫂」は宮尾登美子さんの小説を読む入り口として恰好の作品”と書いている。
「櫂」は喜和という女性の生き様を中心に描いているがこれが始まりであるらしい。
続いて娘の綾子が主体となるらしい「春鐙(しゅんとう)」や「朱夏」、そして喜和の夫が主体の「岩伍覚書」と四部作になっているそうだ。
それぞれ独立した作品ながら全体を1つの長編とみなすことも可能と解説していた。
中でも自分が一番興味を持つのは綾子が主人公らしい「朱夏」で、満州引き上げの苦難が描かれているという。
勿論、他の3作品も興味深いから、順番に時代を追って行くつもりで読んだ方がいいと思う。
少し時間をかけてじっくり読みたいと思うが、何と言っても始まりは林真理子さんなので調べたら宮尾登美子さんのことを書いた「綴る女-評伝・宮尾登美子」と言う林真理子さんの著書もある。
”作家だから作家のことがわかる”と林真理子さんは言っていて、宮尾登美子さんが公表していること全てが事実じゃないという考えもあるようだ。
こちらも凄く気になるので取り敢えず4冊は確保したいと思う。
本は生涯かけてもごく一部しか読めないもので、しかも自分ときたら読んだ先から忘れて行くもので食事をして排泄しているみたいに思うことがある。
何かしら栄養分はどこかにいくらか残っているといいのだが、それもどうなのか。
詠みたい本が4冊も一気に見つかったのが嬉しいし、何だか「櫂」を読んだあとは気持ちが強くなった気がする。
「櫂」の感想を集めた読書メーターも覗いてみた。
色んな感想があって、こんな見方もあるかと考えさせられるけれど、どんな意見や感想もこれが答えというのじゃないからいい。
これが数学だと答えは1つになるけれど、考えは1人1人違っていいわけで、金子みすゞさんの”みんなちがってみんないい”なので気楽なものだ。
「櫂」を読んだ人は当然のように四部作の次に進むみたいだが、「朱夏」から読んで「櫂」に来たという人もいた。
「朱夏」は自分も真っ先に読んでみたい気持ちになっているが、それはこのタイトルが満洲を意味しているのかなと勝手に考えているからだ。
満洲の太陽はとても大きくて大陸が真っ赤に染まるらしく、きっとこちらで眺める太陽とは全然違っているように想像する。
「朱夏」というタイトルが自分の考えと全く違うかもしれないけれど、でも満洲の時代を送って生きて帰った綾子について早く読みたいと思う。
綾子が宮尾登美子さんご自身であるようだが、どこまでが真実なのかは「櫂」の解説でもちょっと微妙な書き方だった。
林真理子さんもそこのところは全てが真実とは限らないような言い方をしていたし、確かに真実なんて誰しもが自身にしか分からなくて当然かと思う。
本屋さんに足を運ぶのが楽しみだ。

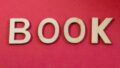

コメント